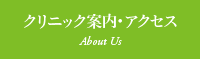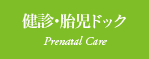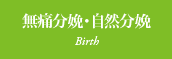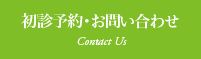妊娠・出産・子育ての役立つ情報
産後・育児の記事一覧
あかちゃんとママの防災
2024年01月26日
2024年になり早いもので1カ月が過ぎようとしています。
今年はお正月から能登半島地震に始まり、さて2024年の日本はどうなってしまうのだろう?と不安を抱いた方も少なくないのではないでしょうか。
日本は数年~数十年に1度、大地震が起こる地震大国の一つなのだと、改めて痛感する出来事でした。そしてまた、日頃の備えをしなければ!ということも感じました。
防災の備えに関して、備蓄用品は最低3日間分を目安に準備し、避難物品はすぐ取り出せる場所に置く。最初の避難のときに持ち出すものは「持てる・使える・助かる」もの。これが基本だそうです。
妊婦さんは、その初期・中期・後期で体調も異なるため、その時期のご自分にあった準備が必要です。また、あかちゃんがいるご家庭も+αの備えが必要になります。
以下のものは、通常の避難バッグの中にプラスして必要と言われている、妊婦さん・産後の方・乳幼児のいるご家庭用の避難用品です。
【妊婦さん・産後】
母子健康手帳、健康保険証、緊急連絡先のメモ(ご家族・病院等)、ゼリー飲料等簡単に摂取できる非常食、マスク、小銭(10円玉、100円玉を500円分程度が公衆電話で便利)、清浄綿、アルコールタイプのウエットティッシュ、生理用ナプキンか新生児用紙おむつ(出血・破水・悪露に備える)、携帯用トイレ、携帯の充電バッテリー、携帯用ラジオ、使い捨てカイロ、バスタオル、大きめのビニール袋、携帯用レインコート(保温に役だつ)、靴下
【乳幼児のいるご家庭】
上記に加え、ミルク(スティックタイプや液体ミルク)、市販の離乳食、アレルギー除去食(アレルギーがある場合)、ガーゼ類、紙おむつ(1日10枚目安)、おしりふき、保温用のタオル類、こどもの着替え、抱っこ紐
近年、地震だけでなく、異常気象などでも避難生活を余儀なくされることがあります。
この機会に、ご自身の住んでいる地域のハザードマップの確認、避難場所の確認、ご家族との連絡方法の確認など行っておくことも大切なのではないでしょうか。
最後に、このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。被害を受けられた皆様の安全と1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。
参考資料:内閣府 あかちゃんとママを守る防災ノート
東京都 東京くらし防災・東京防災
日本助産師会 助産師が行う災害時支援マニュアル
おひなまき
2023年11月27日
今回は「おひなまき」について注意点を交えて少しお話したいと思います。

おひなまきとは、赤ちゃんがママのお腹にいたときに似た姿勢を、おくるみやバスタオルなどの布でくるむことによって再現してあげる方法で、おひなまきでお腹の中にいた時と同じ姿勢をとってあげると安心し眠りにつきやすいと言われています。
赤ちゃんは、生まれてから生後4か月ごろまでは原始反射であるモロー反射などで手足がビクッとなりやすいので、布で巻いてあげると落ち着きやすく、寝かしつけがしやすかったりします。なので、私たち助産師もおひなまきをして赤ちゃんを落ち着かせてあげることもあります。
ただ注意しないといけないこともあります。
おひなまきをしたまま、長時間そのままにしておくと中の熱がこもってしまう可能性があります。それによって何が問題かというと。
私たちの体は、体温がある程度まで上がると、これ以上体温が上がらないように熱を発散させます。おくるみなどで包まれた状態だと発散した熱の逃げる場所がなくなり、包んだ中の温度がどんどん上昇してしまいます。結果さらに体温が上がってしまうということが起こります。
そうなると身体の働きを調整している自律神経の働きである副交感神経が優位になっていき、例えば赤ちゃんの呼吸の数が減っていったり、身体の機能がお休みモードに入ってしまったり、それが続くことによってSIDS(乳幼児突然死症候群)を引き起こす可能性があるのではないかと言われています。
なので、熱をこもらせないためにも、おくるみとかでずっと包んで暑い状態が続くのを避けましょう。
おひなまきをする場合は、定期的に赤ちゃんの様子を見てあげて、お顔が赤くなっていたり、髪の毛が汗で湿っていたり、いつもより呼吸が早かったりした場合には、おくるみを外してあげて熱を逃がしてあげたりとかの対策が必要です。また、寝かしつける時や、泣いている時とかにおひなまきをして、落ち着いたなと思ったら、ちょっとおくるみを解いてあげるのもいいかもしれません。
おひなまきがいけないというわけではないので、上手に使いながら育児に取り入れられるといいですね。
文責 院長

男性の育休(育児休業)
2019年03月15日
厚生労働省は2020年までに男性育休率13%を目標としています。
2017年度の厚生労働省「育児休業取得率」によると、男性5.14%(2016年度 3.16%)と少しずつ上昇していますが、まだ取得率は低いようです。
共働きや核家族の家庭が多く、産後のサポートは夫の協力が必要不可欠です。
育児休業取得のメリットは、母親の育児不安やストレスの軽減、虐待防止や父親としての自覚が高まる。夫婦の間でコミュニケーションも高まり、パートナーシップが強まると言われます。
夫婦一緒に赤ちゃんと過ごすことで、一緒に悩み、相談し、協力しあう「戦友」になるといいですね。パートナーは「敵」ではありません。夫婦ともに子育てをスタートして、安心できる環境作りが大事です。
育児休業のデメリットは
収入が減少・同僚に負担をかける・パタニティハラスメント(会社の上司が、パパになった男性の育児参加を妨害すること)受ける可能性があること。
職場の中で相談や仕事を引き継げるように準備が必要ですね。
虐待の原因に、
・育児に不安がある
・夫が育児に協力してくれない
・孤立した子育てで相談相手がいない
などが、あげられています。
育児は正解がなく、子供も日々成長します。
母親が心配や不安なことを話せて、共感してもらえると、とても安心出来ますね。
妊娠前に産後の生活をイメージするのは難しいですが、
産後に話合うのではなく、日頃から夫婦で会話や相談、準備や下調べが大切ですね。
児童館は面白い
2019年02月18日
児童館は乳幼児とその親御さん、小学生はもちろん中高生までもが集まる場所です。ある児童館は図書館、区民センターも併設されており、大人、高齢者まで幅広い年齢の方たちが触れあえる場所となっているところもあります。
区のホームページや広報誌を見てみると、各児童館のイベント情報が得られます。もちろん、イベントのないときでも開館時間中は、子供たち、親たちの交流の場となります。
出産の予定がある親御さんも対象となっているおもちゃ作りや、ベビーマッサージ体験なども開催されているようです。
手遊びや外遊びを教えてくれたり、食育をテーマにした内容だったり、対象年齢別に様々なイベントが開催されています。
以前そこで働く方たちにお話を伺ったことがあります。今は夫婦だけで子育てしている家庭が多く、親も子供も孤立しがちです。地域のみんなで交流の場を持ちましょう、つながっていきましょう、というのが児童館や、区民センターの方たちの思いです。
幼い頃から児童館に通う子供は、小学生になれば放課後に児童館が行きやすい場所になります。様々な年代の人がいるので、世代を越えた交流が貴重な体験になります。
ぜひお近くの児童館や区民センターを調べてみてください。子育てはひとりで、またはひとつの家庭でしていくものではないことに気づけるはずです。
蚊の季節です
2018年07月09日
この時期から気にかけておきたいのは、蚊の対策です。
蚊は人の体温や吐き出す二酸化炭素を感知して寄ってきます。
また汗をかいた肌は近寄りやすい状態になっています。
人が蚊によく刺される場所は、茂みのある公園や庭の木陰などです。
2014年には首都圏で渡航歴のない人の複数のデング熱患者が報告されました。都内の公園での感染が疑われ、大きなニュースになりました。
このような感染のニュースは大きな心配事となります。
普段から蚊の対策を考えておくとよいでしょう。
蚊はまず繁殖を防ぐことが大切です。
蚊は植木鉢の受け皿やバケツなどに溜まる水でも発生します。
屋外に水がたまるようなもの放置しないだけでも蚊に刺されないようにする対策になります。
外での活動は肌の露出を避け、どうしても露出してしまう手や首には虫よけ剤を使用しましょう。
虫よけにはいろいろなタイプのものがあります。
塗るものだけでもシートタイプ、スプレー、クリームなどがあります。
皮膚につけるタイプのものにはディートという成分が含まれています。
6か月未満の赤ちゃんには使用できないので、よく注意して選びましょう。小さな子供にはハーブの香りで寄せにくくするタイプの虫よけがおすすめです。
また玄関や庭にぶら下げておくもの、電気式薬剤拡散タイプ、室内スプレータイプ、昔ながらの蚊取り線香やアロマオイルなどいろいろなものがあるので、使う人や場所によって使い分けるとよいでしょう。
蚊に刺されると痒くて不快です。ひどいと蕁麻疹などアレルギー症状を引き起こすこともあります。掻きむしらないことも大事です。外出時や屋外での活動のときには、虫よけ対策と同時に、刺されたときに使用できる薬の携帯もおすすめです。
これから本格的な夏がやってきます。
虫よけ対策も万全にして快適に過ごしましょう。
バックナンバー
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (2)
- 2016年2月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (2)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (2)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (1)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (2)
- 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀4-5-1
- 東急田園都市線用賀駅よりタクシー 約5分、徒歩約13分